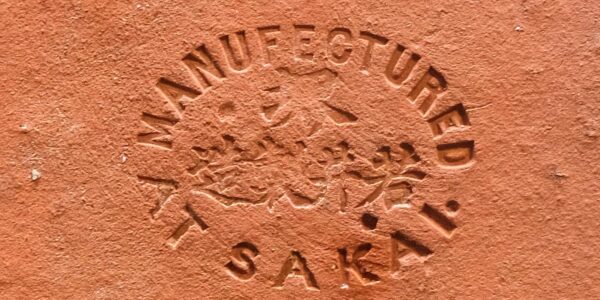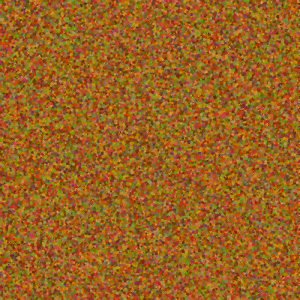金雲母=黒雲母の一種。800℃台前半で溶融。東洋組製品のように焼成温度が低いと結晶状態のまま含まれる。モルタルに含まれていたものも同様。一度溶融し再結晶したものも光をかざすと輝く(琵琶湖疏水製品など)。さらに温度が上がると?褐紫色に変色し光沢を失うようだ。
白雲母=融点1200℃付近。ホフマン窯でも通常はそこまで温度が上がらない故、結晶の状態を保ったまま含まれることになる。
東洋組西尾工場(田原分工場近傍転石):変性していない金雲母を多く含み、裸眼目視でもキラキラ輝いて見える。径1mmほどの大型の結晶も多い。
西尾士族工場時代の製品も溶融した雲母を多く含むが、高温で焼成され変性が進んだのか、光沢を放つものは稀である。含有量は東洋組時代の製品ほど多くはない印象だが融解して胎土に染み込んでいる場合も多いと思う。それよりも環境由来の付着金雲母が多い(西尾の砂に当たり前のように含まれているので西尾市街の転石には必ず付着している)。
刈谷士族工場:微細な白雲母・黒雲母を比較的多く含む。黒雲母はおおかた溶融。写真中右白が白雲母、その左上の紫褐色(その左側のやや黄土色の部分も)溶融雲母。顕微鏡ではもっと鮮明に見えるのだがきれいに撮影するのは困難。褐紫色に変色する前の?溶融→再結晶したものは顕微鏡下では右図のような感じの光沢がある。
刈谷西方を流れる境川の砂には確かに金雲母を含んでいる。それが流れ込む衣浦湾の沿岸工場の製品も含むことが多いようだ(市古製品参照)。


市古工場:黒雲母よりも白雲母の含有量が多い&結晶径が大きい。写真では石英にも見えるが薄く剥離した結晶なので白雲母と思われる。高温で焼かれたものが多く、金雲母はほぼ変性して光沢を失っている。
根崎煉瓦(岡田煉瓦)”□イ二”:西尾とは矢作川を挟んで向かい合う位置にある工場だが、目につくような顕著な雲母は含まれていない。矢作川河岸ではなく北方安城の方の土を使っているのだろうか。
琵琶湖疏水工場(例・ソ二九):1mm以下の微細な溶融雲母を多数含む。溶融しているが形を保ったものが多く、キラキラ輝く点を無数に見ることができる。”□+疏”、”小判型+疏”も同様。奈良平岡窯製品、小島煉瓦、津守煉瓦(小)なども似たような含有のしかたをしたものがあるが、これらについてはその工場の特徴であるかどうかは不明(サンプル数少ない)。
阪府授産所:かなり顕著に金雲母を含有していると見ていたが、表面に付着したものがほとんどで、モルタル由来の金雲母であったかも知れない。断面胎土中に含むものも確かにあったが総量としては西尾製品や琵琶湖疏水工場製品の比ではない。

モルタル由来の金雲母。火が通っていないので金色にキラキラ輝き、六角形に近い結晶形を保つものも多い。針でつつくと剥がれる。